| <Top <BACK NEXT>
|
|
|
「1950年代――カラダの戦後復興は乳房から始まった」(1)
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
| <Top <BACK NEXT>
|
|||
| 本サイトの掲載文ならびに掲載写
真、イラストの無断使用を固く禁じます。 All Rights Reserved.Copyright(C)2000-2003 Motoko Jitsukawa design,illustration&maitenance by ArtWill |
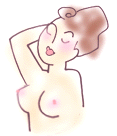 1959年の週刊平凡に「乳房はアクセサリーか?」という記事が掲載された。これは北海道新聞に寄せられた投書をめぐっての議論を題材に、母乳や豊胸手術といった乳房をめぐる問題を取り上げている。そもそもの発端は三十四歳の主婦が、人工栄養で赤ん坊を育てられる時代だからといって、乳房を男性の観賞用のアクセサリーにしていいのか、と憤って投書したことから始まった。これに対して、人工栄養のほうが赤ん坊が大きく育つのだし、母乳をあげると乳房の形が崩れる、女性がいつまでも美しくあろうとするのはいいことなのだから、アクセサリーで何が悪い、という反論が寄せられ、大論争になったというわけ。
1959年の週刊平凡に「乳房はアクセサリーか?」という記事が掲載された。これは北海道新聞に寄せられた投書をめぐっての議論を題材に、母乳や豊胸手術といった乳房をめぐる問題を取り上げている。そもそもの発端は三十四歳の主婦が、人工栄養で赤ん坊を育てられる時代だからといって、乳房を男性の観賞用のアクセサリーにしていいのか、と憤って投書したことから始まった。これに対して、人工栄養のほうが赤ん坊が大きく育つのだし、母乳をあげると乳房の形が崩れる、女性がいつまでも美しくあろうとするのはいいことなのだから、アクセサリーで何が悪い、という反論が寄せられ、大論争になったというわけ。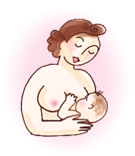 「乳房アクセリー論争」からわかるのは、乳房には二種類ある、ということだ。
「乳房アクセリー論争」からわかるのは、乳房には二種類ある、ということだ。 もう一つは、消費型乳房である。異性・同性を問わず、他者の視線を惹きつけるための乳房だ。また女性としての自信や誇りを感じさせるための乳房である。だから形が問われ、張りが求められ、乳首の形から乳頭間隔にいたるまで問題にされる。より強く視線を誘いこむために、ブラジャーをして形を整え、垂れ下がらないようにマッサージをし、ときには整形手術も施される。お金や労力を消費してできあがる乳房は、他人の視線と自己満足しか生まない。もしかすると子どもと自分を養ってくれる男を獲得する手段になるかもしれないが、男を惹きつけておくために、「形が悪くなる」という理由で母乳を飲ますことはできず、粉ミルクを買わねばならない。あくまでも消費型の乳房なのだ。
もう一つは、消費型乳房である。異性・同性を問わず、他者の視線を惹きつけるための乳房だ。また女性としての自信や誇りを感じさせるための乳房である。だから形が問われ、張りが求められ、乳首の形から乳頭間隔にいたるまで問題にされる。より強く視線を誘いこむために、ブラジャーをして形を整え、垂れ下がらないようにマッサージをし、ときには整形手術も施される。お金や労力を消費してできあがる乳房は、他人の視線と自己満足しか生まない。もしかすると子どもと自分を養ってくれる男を獲得する手段になるかもしれないが、男を惹きつけておくために、「形が悪くなる」という理由で母乳を飲ますことはできず、粉ミルクを買わねばならない。あくまでも消費型の乳房なのだ。
 伊東絹子の人気がもたらした影響はもう一つある。それはカラダの美しさは計測できる、という認識を高めたことだ。彼女のスリーサイズは、86-65-94センチ。身長164センチ、体重52キロ。頭が小さくて、脚が長く、八頭身美人と呼ばれた。
伊東絹子の人気がもたらした影響はもう一つある。それはカラダの美しさは計測できる、という認識を高めたことだ。彼女のスリーサイズは、86-65-94センチ。身長164センチ、体重52キロ。頭が小さくて、脚が長く、八頭身美人と呼ばれた。